数のまとまりをつくり出そう(第12時)
公開日: 2025年11月10日月曜日
本校算数科の内田です。
今回は、5の段との出合いについてお伝えします。
今回の実践では、5の段を最後にもってきました。2の段や3の段を経て扱うことで、被乗数の分配法則に気付くことができると考えたためです。
提示した事象は、あいかさんの5×5と考えた時間割の表です。
5×5にした理由は、交換法則がどのような場合に使えるのかを明確にするため、乗数が大きくない場合は、同数累加や5とびが簡単なことに気付くことができるようにするためです。
解決にうつると、やはり同数累加や5とびによる解決がほとんどでした。ただ、2年生と言いう実態のためか、同じ同数累加の解決でも、表し方や計算過程が異なると、「別の考え」「新しい考え」と捉えてしまいます。
そこで、今回は「これは新しい求め方なの?もう出てきたことがある求め方なの?」と問い返すことにしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
みわ :私は5+5=10。5+5=10。10+10=20。20+5=25でやりました。
C :それって、あいなさん方式じゃない?
C :え?いやちがうんじゃない?
T :これってもう出てきたやり方なのかな?新しいやり方なのかな?
れいあ:あいなさん方式とはちがうと思う。だって、あいなさんは、はじめからまとまりをつくっていて、一気にたしているけど、あまり(5)をたしているから。
T :なるほど。これまで出たのと同じじゃないって人は?
えいた:5のまとまりをつくって、たしている。そして、また5のまとまりをつくっている。
C :あ~。
T :これって新しいの?
しょう:新しいんじゃない?だって、同たし算はおなじやつをたすから。
T :え?同たし算じゃないの?
ゆうた:ちがうよ。だって、5+5=10で、5+5=10で…。
T :じゃあ、みわさんに図もかいてもらおうか。
みわ :(5×5のマスをかく)
T :これ、何ですか?
C :新しい。
れいと:同たし算。5を4つたして、そこに5をたしているから、同たし算だと思う。
C :うーん。
れいと:10と10は、もともと5をたしているから、5を4回たしている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
子どもたちは、やはり「表し方」や「計算過程」が異なれば、異なる考えだと捉えてきているようです。「多様な考え」を大切にしようとすると、どうしても”オリジナル”を追究したり、同じ考え方も違うものとして捉えたりすることがあります。
共に数学的価値を見いだしていくためには、共通点と相違点をしっかりと捉える、つまり、統合的に考察していくことが重要だと思います。どんな見方・考え方を働かせているのか、丁寧に確認していくことが必要だと感じました。また、今回、もしかしたら、ブロックで操作を確かめると、もっとすっきり「同たし算」だと認識できたかもしれません。納得できないときは、操作に戻って意味を捉え直すことを大切にしなければならないと反省しました。
この後、5とびの考え方が出てきましたが、5とびも考え方としては「5を5回たしているもの」として、同たし算と似ていることが明らかになりました。
さらに、りんこさんは5×5=5×(3+2)の分配法則を図で説明しました。子どもたちは、学びの足跡も手がかりにしながら、あいなさんが考えた「分けかけたし算」だと捉えていきました。
 |
| 学びの足跡を見る姿 |
そして、交換法則(はんたいほう)は、同じ数をかけているからできないことを確認しました。他にも、りんこさんと同じ考えの子どもに、「どうして分けかけたし算をしたの?」と尋ねると、「10ができて計算しやすいから」と話してくれました。
少しずつ、「自分にとって解決しやすいもの」を考えて、自力解決したり、対話したりする姿が見られるようになってきたように思います。次時は、他の5の段を構成したいと思います。その上で、「考えのよさ」にも着目できればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
 |
| 第12時の板書 |
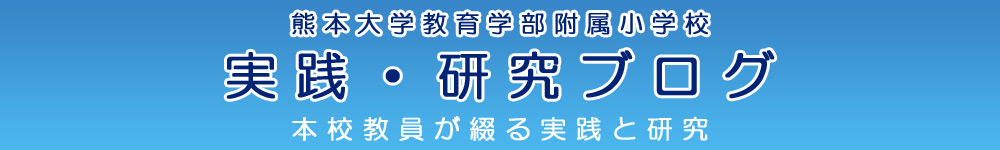
0 件のコメント :
コメントを投稿