6年 比 「くじ引きゲームをプロデュース!」第8時(校内研本時)
公開日: 2025年5月28日水曜日
算数科の津川です。
先週、こちらで紹介している「比」の単元の8時間目がありました。
今回は、2つのくじ引き同士を足し合わせる際の比を考えることで、「どうして比同士を足してはいけないのか」全体量を捉えた上で、外延量と内包量の違いを見いだすことをねらっていました。
この時間は、「様々なくじを面白くするアイデア」の中から多くあった話題の1つを取り上げるところから始めました。
T「この前くじを作ったよね、くじが少なかったってあったんだよね」
CC「あ〜」
T「増やしてあげたいところなんだけど、これ以上は先生からあげることはできないんだよね」
C「球を作ればいいんじゃないかなあ」
C「どうやって作るの?」
ここで一人の子の振り返りを取り上げました。
C「このくじ引きの箱いっぱいにしたいって言ってたんだよね」
T「この箱の中、半分くらいくじ引きの玉で埋めたいって書いていたんだよね」
C「あ〜〜」
C「じゃあみんなから球を集めてこないと」
C「2班に1つとか」
ここで、2つのくじ引きを合わせるといいのではないかという視点が出てきたので、もう一度みんなに伝えるように促しました。
C「あ〜〜」
T「今のイメージできた?」
C「14だから28かあ」
C「1:13だったら・・・」
C「合計の数が変わるよね」
T「今、合計の数が変わるって聞こえてきたけど・・・」
C「何個までだったけ?」
C「16個までだから・・・」
C「じゃあ、最大32個になるよ」
C「32かあ。おーー」
T「変わるものって合計の数だけかな?」
合計の数だけでない、比の要素にも目を向けさせようとしました。
C「あたりの確率も変わるよ」
C「確率が同じならば、足しても変わらないね」
C「割合が同じだったら、変わらないよ」
C「プラスマイナス、ゼロになるね」
C「どっちも数が同じだったら変わらないんじゃないかな?」
T「比って変わるのかな?、変わらないって言葉も聞こえてきたけれど」
C「変わらないこともないと思う」
C「数が同じだったら変わらないよ」
C「数が違ったら変わるよ」
ここで、例として箱を提示しました。
T「試しにさ、ここにAのくじがあります、4:3です」
C「たくさん当たる」
T「たくさん当たる?」
C「どっちが当たりですか?どっちが当たりかで変わる」
T「4が当たりです」
CC「えーーー!?」
C「じゃあたくさん当たる」
C「Aが当たりなら、125%当たる?」
T「Bは1:2で当たります」
C「こっちが普通だよ」
C「祭りのくじとかは当たりにくいもんね」
C「これだと5:5になって・・・」
C「これ合わせたら半分になって・・・」
C「半分じゃなくない?3分の1だから」
C「7分の1と3分の1だから」
C「これ合体したら半分になるよ」
C「ならないよ」
比同士を足したら半分になるんじゃないかという予想が出てきたので、近くの人とどうしてそのような考えが出てきたかを話し合う時間をとりました。
C「個数が知りたいかも」
C「3分の1だからなあ」
C「5:5だから、つまり1:1だよね」
一人の子が黒板に演算子を書き足しました。
C「そうそう!そうなるよ」
C「これいいのかな?」
C「AとBの数が違ったら意味ないんじゃ?」
C「でも、5:5ってこういう意味だよね」
C「10個中の5個で、5個がハズレだよ」
T「違うって思っている人もいるわけだね、ちなみに5:5ってなんだった?」
C「1:1になります」
C「50%です」
C「2回引いたら、1回当たります」
C「かもしれないね」
ここで実際に前で足し合わせて、10回引いてみる時間をとりました。
C「これだと5分の1しか当たらない」
C「全体が10だとすると2しか当たらないよ」
C「これ本当に同じ数かなあ」
T「10のうち2回しか当たらなかったんだね」
ここの比の表現とその前の比の表現は、当たり:ハズレと、当たり:全体の数で様相が違います。この1:5の比の下にその比の説明を書き加えるなどの手立てをしておくと、全体の数をより意識できたように感じました。
C「でも確率が違うよ」
C「たまたまだと思う」
C「偶然だよ」
C「先生、早く確かめたいです」
T「1:1じゃなかったね」
C「確率上は1:1でも」
C「やっぱり運要素があるからね」
C「全部の数がわからないとダメだよ」
C「何回かして平均するといいよ」
ここで自分の立場を決めました。
ほとんどの子どもが1:1じゃないと思う方に手を挙げました。
T「じゃあ、本当に1:1か、1:1じゃないと思う人はどうして1:1じゃないのか、ノートに考えをかいてみようか」
ここで、課題はたったように感じているのですが、黒板に言葉を書く際に葛藤しました。多くの子が「1:1ではない」と予想していたため、「どうして1:1ではないの」とより数学的表現を引き出すことができる言葉にしたのですが、実際この場面の空気感は「本当の比は何?」の方が改めて考えても近かったように感じています。
一度、班で考える時間をとりました。
れいと「先生のインチキなのかな?」
T「インチキ?」
なつき「インチキ?」
しんじ「そうかも」
しんじ「何対何って書いた?」
れいと「4:3と1:2だよ」
しんじ「比同士を足したら、5:5で、1:1かあ」
れいと「足していいのかなあ」
しんじ「1の大きさが違うのかな」
なつき「1の大きさが違うってよ(れいとさんの方を見て)」
それぞれの班、AとBのくじの比を基にして割合で比較したり、等しい比の関係を用いて考えたりと様々だったので、一度全体の量を意識させてたいと考え、このタイミングで、以下の考えを共有しました。
C「合計」
C「比の和」
次に以下の考えを書かせました。
C「玉の個数?」
C「当たり玉が12個・・・」
C「どういうこと?」
C「何で10個と14個?」
C「だから、1:2じゃん。そこから10個と20個だよ」
C「どうして10個と20個にしちゃったの?」
T「例えばで出してくれたのかな?」
C「仮定しちゃっていいの?」
T「これ、1:1になってる?」
C「なってない」
子どもたち同士で、「どうして」と言いながら対話が促進された瞬間だったと感じています。私自身、子どもたちがどう出るかを待ってみようと思って途中話さなかったのですが、これまで会話の解像度を上げようと、教師が間に入りすぎている瞬間があったなと改めて反省したところです。
ここで、具体的な数の話も出てきましたので、2班に1セットずつ用意しているAとBの箱セットを用いて考えてもいいことを伝えました。(子どもたちは事前にその箱の存在は知りませんでした)
しんじ「箱を取りに行こうかな」
れいと「ハズレ、ハズレ、ハズレ・・・」
しんじ「混ぜてみよう」
しんじ「割合はどうなるかな?」
ここから何度かくじ引きを試行してみる様子が見られました。
しんじ「ハズレだけ取り出してみようよ」
しんじ「あたりは13だね」
C「あたりとハズレは13:16だね」
なつき「1:1ではないよね」
C「そうだね」
ここで、どうして比同士を足してはいけないのか様々なアイデアが出てきたので、全体でそのアイデアの交流を図りました。
T「1:1だった?」
C「必ずしも1:1にはならなかった」
C「13:16だった」
C「Aは8個と6個」
C「Bは両方とも5倍で5個と10個」
C「Aはどちらとも2倍」
T「どうして比を足してはいけなかったんだろうね」
C「どちらも比の和を揃えるといいと思います。それぞれの比の和の最小公倍数は21だから、そうするために、Aを3倍、つまり12個と9個、Bを7倍、7個と14個にすると19:23になりました」
T「21個、42個と数が揃うようにしてもうまくいかなかったってことかな?」
C「ちょっと似てるんだけど・・・」
下の写真のように黄色と青で印を付けました。
C「価値の大きさ」
C「Aの4とBの1は価値が違うというか、比の値が変わってるから・・・」
C「価値というか、値が違う」
T「1つあたりってなんだろう」
C「Aが2個でBが5個」
ここで、この1つあたりの計算方法について、確認を行いました。
C「4と10は、簡単な比にすると2:5になる」
C「8÷4とと5÷1」
C「そっか、本当の数をあたりの比で割っているよ」
C「これだと、ハズレも同じ計算を考えることができるよ」
T「2つのくじを足し合わせるときの比ってどうすればよさそうなんだろうね」
C「比の和を同じにするのかな?」
C「何倍を同じにするといいよ」
C「例えば、今回だったらAを8:6にするとBが2と4になるとできると思う」
T「AとBの本当の比を求めるにはどうすればよかった?」
C「数を数えるとよさそう」
T「今他の数でも試してみたいって言葉も聞こえてきてるけど、本当にこれが成り立っているのかな?」
ここで、モニタリングシートを提示しました。
T「自分の班と他の班、どこを足せばいいかなっていうのも考えてみましょう」
しんじ「うちの班は何個だったっけ?」
なつき「16個だったよ」
しんじ「他の班は14個にしてキリよくしたいよね」
なつき「(3:11の班を指して)どっちかじゃない?」
T「どこと足したらよさそう?」
れいと「ここかなあ」
ここで、一人の子の考えを取り上げました。
T「さっき気づいたことを言ってもらってもいい?」
C「1:13とか3:11はそのまま個数になっているところがある。そのまま個数になっているところは比同士を足せるよ」
C「簡単な整数の比のところ同士とか・・・」
C「同じ比の値のところは、そのままになりそう」
ここから算数図日記を書く時間をとりました。
自分の中で、同じ個数ならできると仮定を立てて、試してたようです。他の数でもやってみたいと考えていることから、もっと幅広い数値がモニタリングシートにあってもよかったなと感じました。(個数が14個で1:6の班が多かったです)
今回の実践により、「課題の立ち上げ」について見えてきた新たな成果と課題があります。さらに、子どもたち同士が自分のアイデアを伝え合う道具(数学的表現)の想定がまだまだ甘かったなと反省しています。
6年生の学びはまだ始まったばかりですので、これからも普段の授業において、研究を続けて参りたいと思います。
その成果を、研究発表会でお見せすることができればと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
算数科 津川
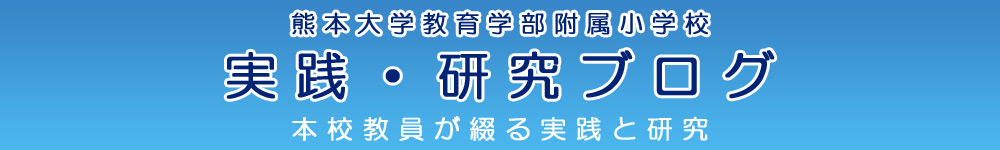

















0 件のコメント :
コメントを投稿