数のまとまりをつくり出そう(第13時)
公開日: 2025年11月10日月曜日
本校算数科の内田です。
今日は、5の段の構成についてお伝えします。
これまで、2・4・3の段の構成をしてきた子どもたちは、目の前の事象の数やそれぞれの段の積を多様な方法で求めてきました。その中で、少しずつ、多様な方法を比較していく姿が増えてきました。次時の3×15へのつながりを考えた時、「既知のことを用いて未知のことを明らかにしている」という気付きや多様な方法に対する「よさ」の考察が本時で重要になると考えました。
同数累加や5とびを分かりやすいと考えている子どもたちにとっては、3×15で同じ方法を用いるとかなり時間がかかります。このような子どもたちが「よりよい方法」を考えるためには、「既知のことを用いる」ことについて、気付いておくことが必要です。そして、3×15の時に実際にそのよさを感じて欲しいと思います。
そこで、本時では、5×7の積を考えることにしました。5×9と迷ったのですが、5×5=25を活用することを考えるならば、「5×5+5+5」の方が、「5×5+5+5+5+5」よりも表出しやすいと思ったからです。
子どもたちは次の順番で考えを発表していきました。
①あやこ:同数累加(同たし算)
②えいじ:交換法則(はんたいほう)
③しょうた:途中から乗法の性質を使う方法(5×5+10)
④れいあ:分配法則(分けかけたし算 5×4+5×3)
②を扱った際には、自力解決の際に「できたけど…、難しい」と言っていた、えいじさんを取り上げ、「7をたしていくのは難しい」という点を明らかにしました。このようにして、繰り上りがあることで少し難しくなることを確認しました。また、③については式のみを提示し、②で使ったアレイ図と関連付けながら、考え方を明らかにしていきました。そして、③について式が出てきたときに「どういう考えなのか?」と問い返すと、えいたさんが、「5×5は習っているから…」と発言しました。最後に④のれいあさんの考えを取り上げました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
れいあ:(アレイ図をかき、7を4と3にわける)
まず、5×4にして20で、5×3=15でたして35。
T :どんなところを工夫したんだっけ?
れいあ:20+15なら、十の位だけでよくて、繰り上がりがないから…。
C :あ~!
T :どういう風にわけたの?
しょう:繰り上がりがないようにしている。
T :でもれいあさんは、分け方にも注目したんだよなぁ。
えいた:習っているやつを使ってる。5×4=20も、5×3=15も分かってる。
しょう:あ~!そういうことか!こっちは5×3!習っているやつ!
えいじ:そっか!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
子どもたちは、③と④の考えの検討を通して、「既知のことを用いて未知のことを明らかにする」ということに気付いていきました。一方で、「よさ」については、計算のしやすさに向かっている姿(ぴったりになる、繰り上がりがない)もありました。この「よさ」の捉えが、次時においては、例えば、「計算回数が少ない」「分かっていることを使っているから計算がはやい」のようなところまで言及できればいいなと思います。そうすれば、乗法の性質や計算法則を意図的に用いる姿につながってくると考えます。
次時において、子どもたちが自分なりのお気に入りを語りつつ、共に「よさ」を見いだす姿が生まれてくればいいなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
 |
| 第13時の板書 |
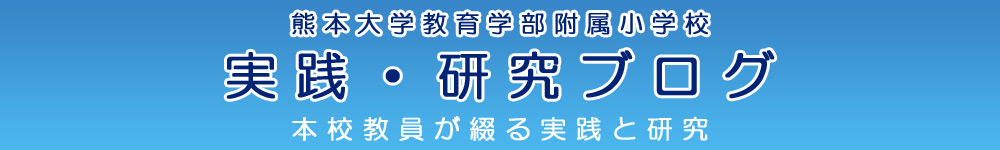
0 件のコメント :
コメントを投稿