数のまとまりをつくり出そう(第6時~7時)
公開日: 2025年11月4日火曜日
本校算数科の内田です。今回は、2の段の構成についてお伝えします。
前時で、日常の中にある数のまとまり(かけ算)を見付けてきた子どもたち。
それらを見てみると、2×□や4×□のものが多くありました。特に 2×□が多く、子どもたちにとって、「2のまとまり」が見付けやすいことが分かりました。
また、本単元の導入の影響からか、ほぼすべての事象が「並んでいるもの」から見付けていました。つまり、教科書にあるような「箱の中にお菓子が6つあって、その箱が4つある」のような場面を見付ける子はいませんでした。
かけ算はたし算とは異なり、式によって、その並び方まで伝えることができることが特徴なので、子どもたちはその特徴を捉えていることができているのかもしれません。
しかし、「1つ分」や「いくつ分」を明確に捉えることも大事にしなければ、九九の構成において、交換法則やかけ算の性質を用いることにつながらない可能性もあります。(より大きな数のまとまりの同数累加によって解決してしまう)
そこで、2の段及び4の段では、「1つ分」が出来る限り明確なものを取り上げることにしました。
第6時で取り上げたのは、次の写真です。
まず、2×5のトイレのスリッパを提示し、「2のまとまりが5こ」であることを確認し、さらに多い2×8の写真を提示することで、「2のまとまり」に着目した求め方への動機付けを高めました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T :どうやって求めたか、教えてください。
しょう:2を8回たして、2+2+2++2=16
れいあ:そうそう。2・4・6・8っていうようになって16。
りいさ:図でやって…(②のまとまりを8つかく)
それで、片方ずつをたすと8+8=16
T :りいささんの図は面白いね。これまでは1つを〇で表していたけど、まとめて②ってしたんだ。ブロックでやってみた人は、どうなったの?
わくと:(ブロックを2×8に並べる)
T :ここに、「8」は見える?
(ゆりえが下側を数える)
T :そっか。この2のまとまりが8こ、並んでいるんだね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このようにして、「2のまとまり」に着目しながら解決する姿がありました。しかし、りいささんのように8のまとまりに変えたり、ブロックで4のまとまりをつくったりする姿もありました。かけ算の意味や性質に基づいて考えているよりも、なんとなく「自分が答えを求めやすいようなまとまり」に変えているようにも思います。このような「なんとなく」ではなく、意図的にかけ算の意味や性質、計算法則に基づいて解決する姿を目指していきたいと改めて感じました。
 |
| 第6時の板書 |
第7時では、「どんな2×?を見付けた?」と問うことから始めました。子どもたちから、2×1から2×5のかけ算が出てきたので、それらを解決することにしました。2×1から順番に調べ、その数の並びに着目することで、
① かける数が1ずつ増え、答えが2ずつ増えていること
①' まとまりの数(かけられる数)ずつ増えること
② 前の答えに2をたすと、次の2×?の答えが明らかになること
を発見していきました。その後、ブロックで数の増え方を確認し、2×10まで明らかにしていきました。なぜ、2×10かというと、子どもたちいわく、「そこまで分かっておくとなんだか便利そう」ということでした。(子どもたちは、感覚的に「10」が好きなんだろうと思います)
 |
| 第7時の板書 |
第7時において、同数累加による解決に慣れる子どもたちが増えてきたように思います。つまり、1つ分×いくつ分がだいぶ見えてきたようでした。図やブロックによる解決をたくさんしてきた本学級の子どもたちだからこそ、図やブロックに表現した際に、異なるまとまりにして、少ない回数でのたし算を目指す姿がありました。
もしかしたら、かけ算の学習は、子どもたちと教師で活動の目的が異なる場面が出てくるのかもしれないと思いました。
子どもたちは、2×□としての場面に対して、「分かりやすく」「簡単に」答えを求めたいとしている一方で、教師は、九九の構成につなげたいと思っているのであれば、図やブロックを使った時に、「見ようとしているもの」が違うかもしれないということです。
このような子どもと教師のずれをなくすためには、やはり、かけ算⑴では、まとまりをつくり出して、様々な解決方略で数を明らかにする。かけ算⑵では、「様々な解決方略」を用いて九九を構成する。というように2つの大単元における「目的」を大事にする必要があるのではないでしょうか。
考察が長くなりましたが、このことも意識しながら、残り3・4・5の段の学習を進めていきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
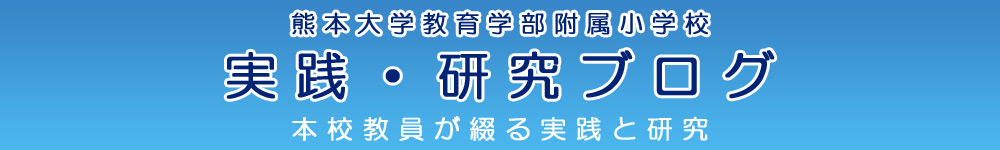



0 件のコメント :
コメントを投稿